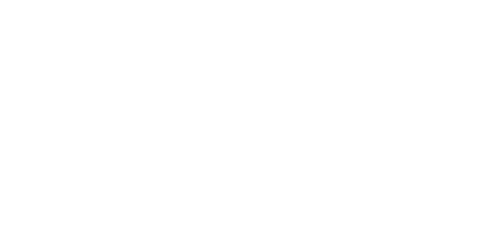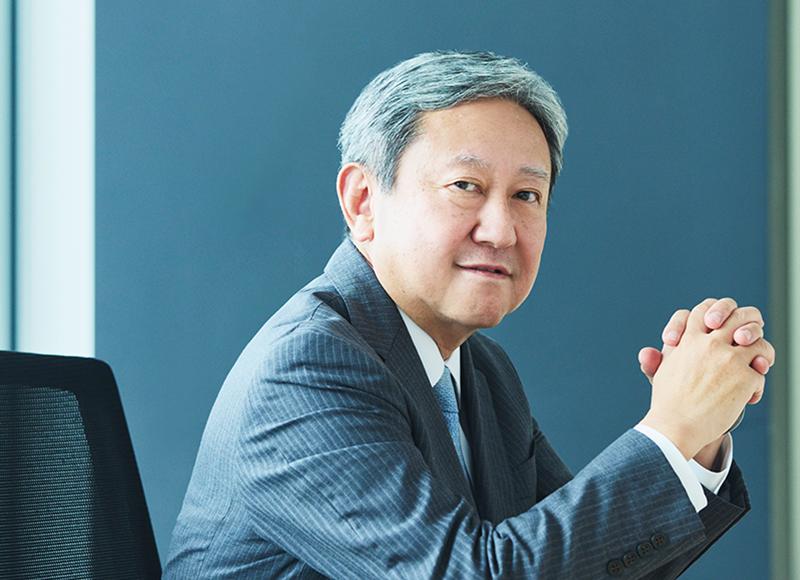
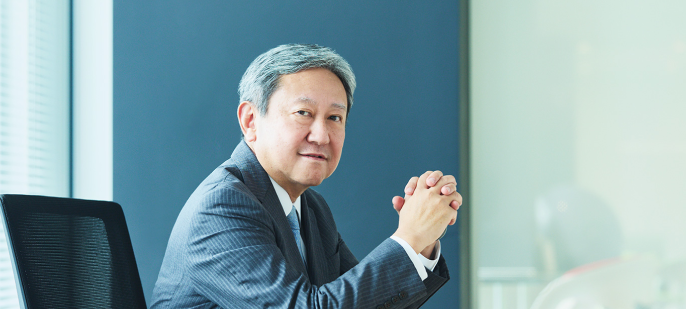
当社グループは「グリーン・スペシャリティの化学会社」に向けた変革を目指しています。2024年6月に当社グループの社外取締役に就任された3名に、取締役会議長の藤原が企業の変革に重要な視点や自身の役割について伺いました。
(2024年7月実施)
取締役会議長藤原 謙
三菱ケミカルグループの印象
- 藤原
- 皆さんは取締役に就任されたばかりですが、当社グループにはどのような印象をお持ちでしょうか。
- 坂本
- 私は化学業界の同業、取引先の立場から長年見てきましたが、MCGグループは事業領域が広くて深く、我が国における化学産業でNo.1のリーディングカンパニーだと以前から認識していました。高い技術力を用いて、石化製品、機能素材、ヘルスケアなどの幅広い領域で真正面から社会課題に取り組んでおり、さらなる成長のポテンシャルを有しているグループです。これまでお付き合いさせていただいた社員の皆さんも素晴らしい方々ばかりで、この人財の力もMCGグループの競争力の源泉の一つだと感じていました。

- 江藤
- 私はこれまでビジネスでの直接的な関わりはありませんでしたが、もちろん化学産業で国内最大の企業という認識はありました。就任後にレクチャーをしていただく中で、開発・生産両面の技術力への自信を持っていることを印象として受けています。そこから生み出すイノベーションを起点に、いかに社会に貢献できるのかをずっと模索してきた使命感が、KAITEKIというPurposeに表されているのだと理解しています。
- コーツ
- 私はこれまで20年近くMCGグループと関係を築いてきました。コーネル大学の私の研究室にMCGグループの研究者を受け入れてきたことや、技術面でアドバイザリーボードに参加したことがありますが、MCGグループの研究の質や独創性、研究者の能力にいつも感心していました。また、事業ポートフォリオが多岐にわたっているのは欧米の化学メーカーと比べて特異な点です。KAITEKIを実現するためには多くの環境・社会課題に対処する必要がありますが、多様な事業ポートフォリオと技術に裏付けられたイノベーションを掛け合わせることで、MCGグループはKAITEKIを実現できると考えています。
MCGグループの変革について
- 藤原
- 当社グループは持続的な成長に向け、事業ポートフォリオなどの変革を進めようとしています。経営経験の豊富な江藤さん、坂本さんは、企業の変革という観点では何が大切だと考えていらっしゃいますか。
- 江藤
- 将来を見据えて何をどう変革させるのかを明確にした上で、事業の選択を行い、適切にリソースを配分することが大切です。事業の選択は、MCGグループがバリューチェーンのどこで自らの貢献度合いを最大化し、その結果差別化された企業ブランドとして社会に受け入れられるかを見極めることでできるようになるでしょう。ただし、選んだ事業で勝ち残るために競争力の強化も重要です。また変革を進める前提として、確固とした財務基盤も必要となります。

- 坂本
- 企業が存続し持続的に成長するためには、環境変化に適応し世の中のニーズに応えられるよう、事業変革の努力を継続しなければなりません。よく言われるように、生き残り続けることができるのは最も大きい企業でも最も強い企業でもなく、変化に適応できる企業です。またその時々の市場環境に応じて、各事業の最適なオーナーは誰なのかを見極め、必要に応じて事業ポートフォリオを組み換えていく必要があります。
パートナー企業の存在も非常に重要です。かつてのMCGグループは、どちらかと言えば独自で事業基盤を築いて成長してきた印象がありますが、これから新たな事業を創出し育てる上では、他社との協業をこれまで以上に積極的に進める必要があると思います。
変革が求められているのはMCGグループだけでなく、国内の化学業界全体だと私は考えています。欧米に比べて日本の化学業界は、雇用面の難しさもあってこれまで業界再編があまり進んでおらず、その他の要因とも相まって利益率が相対的に低い傾向にあります。
- 江藤
- パートナー企業との協力は確かに重要ですね。共同研究など、自社だけでは賄えない部分を補い合うことで、限られたリソースの中でも成果を最大化することができます。
また業界全体の収益性が低い場合、単に競争に勝てばよいわけではなく、正しい課題設定をしなくてはなりません。そのためには突き詰めた議論が必要でしょう。
- 藤原
- ありがとうございます。変革の先には、KAITEKIの実現をリードする「グリーン・スペシャリティの化学会社」になることを見据えているのですが、この方向性については社外取締役の立場としてどのように思われますか。
- コーツ
- プラスチックのように社会に必要不可欠な素材であっても、製造からエンドオブライフに至るまで環境に大きな負荷がかかっている場合があります。一方で環境に配慮して製造すると、今度は費用が高くついてしまうことがしばしばあります。環境を守り、収益性も確保する持続可能な素材の開発が求められています。
MCGグループは世界有数の優れた化学プロセスを有しています。環境負荷が少なく、安価な費用でMMAを製造する新エチレン法(アルファ法)を皮切りに、そのほかにも環境に配慮し、経済性の高い製造プロセスを生み出していくことで、KAITEKIな社会の実現に近づけるはずです。

- 坂本
- 環境を意識し、循環型社会を志向して事業を行うことは必要不可欠です。一方で、グリーン事業で収益を上げるビジネスモデルの構築はまだ道半ばだと思います。グリーン事業といえどもビジネスとして独り立ちできるような将来像を描き、その実現に向けて取り組むことが大切でしょう。
- 江藤
- グリーン・スペシャリティへの取り組みは化学会社にとっていわば「入場券」、つまり事業活動の必要条件になろうとしていますが、取り組んだからといって生き残れることが保証されるわけではありません。初めは国からの公的支援があるとしても、ずっと続くわけではないため、自立して収益を生み出せるようにならないとビジネス自体が持続可能になりません。
- 藤原
- おっしゃる通り、環境・社会への貢献だけでなく、収益の追求も事業としては不可欠ですね。当社が変革を進めていくにあたって、取締役会等でどのような視点からモニタリングを行ったり、アドバイスをいただけそうでしょうか。
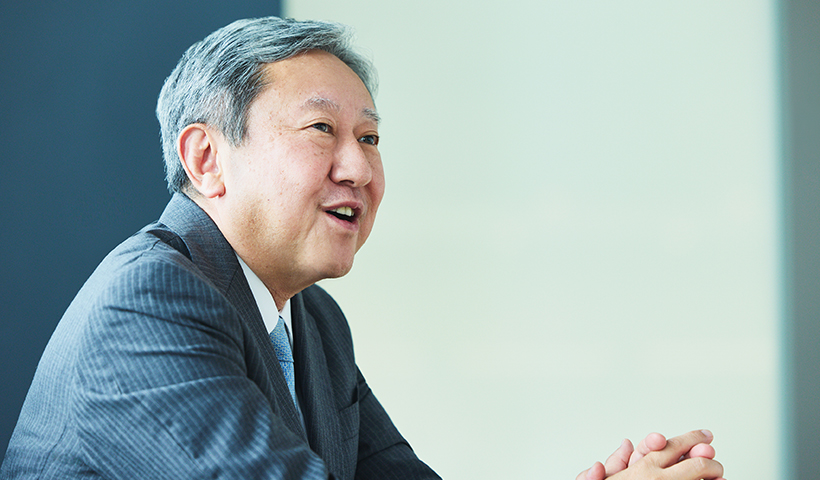
- 坂本
- 欧米の化学業界は先行事例として参考になると思います。かつては欧米の化学メーカーも今の日本企業と同様に収益性の改善に取り組んでいましたが、事業オーナーを組み替える合従連衡を繰り返すことで業態を変革し利益率を改善してきました。当社の将来像を検討する際にはそうしたさまざまな可能性も念頭に置きながら、最適な事業ポートフォリオとはどのようなものなのかを執行サイドに考えていただけるよう、適切な問いを立てていきたいと思います。
- 江藤
- 社外取締役として、執行サイドがどのような視点で事業ポートフォリオ等の変革を進めようとしているのか、ポイントを押さえて議論できているかを確認したいと考えています。事業のベストオーナーを見極める際には、自分たちがその事業を行う上で何が障壁になるのかを客観的に考えることで、続けるべき事業が自ずと見えてくるはずです。各事業とも投資規模が非常に大きく、意思決定の責任はとても大きいと理解しているので、執行の皆さんが最適な行動を選択できるようサポートしていきたいと思います。
- コーツ
- 私もお二人と同様に、どの領域で事業を拡大すべきか、あるいは縮小・撤退するべきかについて、化学技術と収益性の両面から助言したいと考えています。新たな素材の開発では、短期、中期、長期それぞれの視点から慎重な投資判断が求められます。私は、専門領域の一つである技術経済性分析(Techno-economic Analysis)と呼ばれる手法を用いて、技術の導入がもたらす経済性を評価し、執行サイドの意思決定をサポートできると考えています。MCGグループにとって、グリーン・スペシャリティの事業が持続可能となるよう尽力します。
社外取締役としての抱負
- 藤原
- 最後に改めて、社外取締役としての抱負をお聞かせください。
- 坂本
- MCGグループの事業について理解を深め、取締役会などを通じて得られた情報をもとに、企業価値の増大や社会課題の解決のために、あえて空気を読まずに正論を述べて議論の活性化に貢献していきたいと考えています。その際には株主だけでなく、あらゆるステークホルダー、特にKAITEKIの実現をめざす主体である従業員にとって、何がKAITEKIにつながるのかといった観点も意識したいと思います。それが最終的に株主の負託にも応えることになると考えるからです。
- 江藤
- MCGグループの価値向上に貢献する、この一点に尽きます。限られたリソースをどの時間軸で適切に成長投資に配分するかなど、MCGグループのエクイティストーリーを執行サイドの皆さんに確認していきたいと考えています。まずは2024年秋に発表予定の中期経営計画に向けて、取締役会やそれ以外のミーティングの場も活用して意見交換していくつもりです。
また、全てのステークホルダーに最良の配分で成果をもたらせられるよう執行サイドとコミュニケーションをとることも社外取締役の役目だと考えています。時には物申し、時には一緒に悩みながら、MCGグループの成長に必要な議論を行い、執行サイドの皆さんが従来の考えや方針を再考察するきっかけになるような気づきを提供していくよう努めます。
- コーツ
- 私は筑本社長から、MCGグループを「グリーン・スペシャリティの化学会社」に変革したいのだと伺い、社外取締役を務めることを決めました。この変革は簡単に成し遂げられるものではありませんが、MCGグループには実現させる強い意志とケイパビリティがあります。私の科学者として培ってきた知見や素材開発の経験を活かし、MCGグループが化学の分野で世界的なリーダーに成長できるよう貢献したいと考えています。そのプロセスの中で、KAITEKIが実現され、あらゆるステークホルダーに社会的・経済的な価値が提供できると確信しています。
- 江藤
- MCGグループのガバナンスのあり方についても検討していければと思っています。国内では数少ない指名委員会等設置会社として、トップの人事権や戦略への拒否権も持つ強いモニタリング型をめざすのか、あるいは、あくまでステークホルダーの意見を代弁しながら執行サイドと連携する伴走型をめざすのか、意見交換していきたいですね。
- 坂本
- ガバナンスに関しては形式上の体制の選択も大切ですが、それよりも重要なのは、十分な議論ができる経営チームをいかにしてつくり上げていけるかだと思います。MCGグループにとって最適な、実効性のあるガバナンスのあり方を経営幹部の皆さんとの議論を通じて模索していきたいですね。