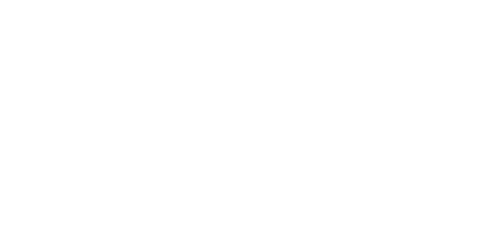社長就任にあたって
そのために2024年春、大掛かりな執行役および執行役員人事も実施しました。現場力重視かつ成長をめざす新チームのもと、「稼ぐ力」の抜本的向上をめざします。
新たな経営ビジョン・中期経営計画の策定へ
私も策定に携わり、2020年に発表した「KAITEKI Vision 30(KV30)」は、2050年にめざす社会像から課題を抽出して2030年のあるべき企業像をバックキャストし、当社グループが取り組む社会課題と事業領域を明確化したビジョンでした。しかし、策定後まもなく温室効果ガス(GHG)排出削減目標の引き上げや再生可能エネルギーの普及など、予測していた将来トレンドが大幅に前倒しになりました。また、AIの社会実装やパンデミックによる社会活動の変化など想定が及ばなかった変化もありました。世界が大きな転機を迎えているこの状況を踏まえ、私たちはいよいよ2024年秋の発表に向けて、新たな経営ビジョン「KAITEKI Vision 35(KV35)」(仮称)およびこれに基づく新中期経営計画(以下、新中計)の策定を現在進めています。
まもなく発表するKV35の基本思想を要約すれば、KAITEKIの実現をリードする「グリーン・スペシャリティの化学会社」への変身です。高機能材料へのシフトを進めつつ、KAITEKI実現やグリーン化という、より大きな枠組みの中でこれを捉え直そうというものです。
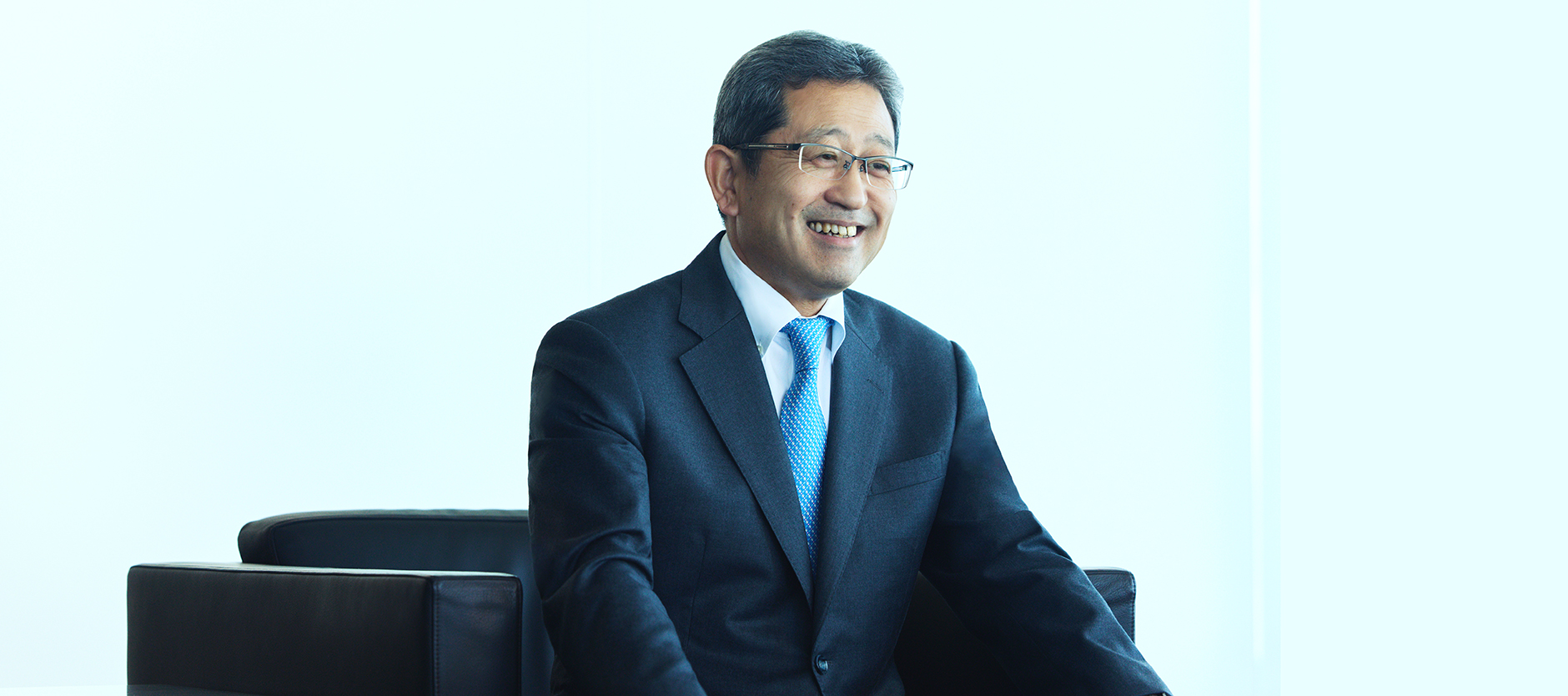
選択と集中の事業ポートフォリオ戦略
スペシャリティマテリアルズ:得意分野にリソースを集中
高機能材料を扱う、今後の成長戦略の大きな柱となる事業です。ただし現状に目を向けると、競合他社に比べ全般的に利益率が低く、収益・利益ともに伸び悩んでいます。その要因として過去の総花的な投資スタンスが大きく影響していると見ています。重要なのは、得意分野にリソースを集中し、ポートフォリオマネジメントを徹底することです。
私たちが必ずしも得意ではない事業については、期限を定めて見極めを行い、売却・撤退の検討を進めています。こうして確保した資金を、当社の得意分野における成長投資の原資とする計画です。注力すべき得意分野として、例えば半導体向けでは、シリコンウエハー製造工程で用いる合成石英や、フォトレジスト用原料ポリマー、半導体封止材用エポキシ樹脂、高純度薬液、半導体装置部品の精密洗浄サービス、次世代型半導体基盤として期待される窒化ガリウムなどがあります。食品向けでは、シュガーエステル、ビタミンEや食品包装用フィルムなど、食品のロングライフを可能にし、フードロス削減に貢献できる製品を取り揃えています。また、EV/モビリティ向けでは炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の成形等、自動車部材分野におけるさまざまな技術的知識とノウハウを有するC.P.C. S.r.l.社の全株式を取得、バッテリー材料についても能力増強を進める等サプライチェーンの強化・拡大を進めています。こうした当社が強みを発揮できる分野に投資を集中し、シェア・収益性の向上を果たした上で、周辺領域の拡大を図ります。
組織体制の面では、2024年4月に大掛かりな再編を実施しました。従来の3つのサブセグメントを「アドバンストフィルムズ&ポリマーズ」「アドバンストソリューションズ」「アドバンストコンポジット&シェイプス」に改称・改組するとともに、それぞれに統括本部を設置、経験豊富な3人の執行役員を統括本部長に配しました。現場に精通した新執行部のもと、多岐にわたる製品分野に目配りし、きめ細かい施策を展開していきます。
産業ガス/ファーマ:本業とのシナジーを精査
ともにグループ業績を大きく牽引する事業です。このうち、日本酸素ホールディングス㈱による産業ガス事業については、シナジーは今のところ、それ程大きくありません。しかしながら、産業ガスは顧客の製造工程の効率化やエネルギー効率の向上に寄与し、CNへ貢献していることや、その着実な利益成長については高く評価しています。また、高品質なガスとトータルソリューションの提供は市場からも認められており、Rapidus㈱が北海道千歳市に建設予定の次世代半導体工場パイロットラインへの供給が新たに決定しています。
田辺三菱製薬㈱によるファーマ事業も同様に化学事業とのシナジーに関しては大きくありませんが、その新薬創出力は内外から高く評価され、米国において希少疾病用医薬品にも指定された筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬RADICAVA ORS®経口懸濁剤は、販売好調を維持しています。一方、売上収益の大部分を占める国内医薬品事業においては、薬価制度の影響もあり、事業基盤の維持が今後の課題です。RADICAVA ORS®の次を担う製品を創出するとともにさらなる成長を実現するため、各種合理化策やグローバル市場における成長戦略の策定を進めていきます。
MMA&デリバティブズ:世界シェアNo.1の強みを発揮
主要3製法を世界で唯一保有する世界シェアNo.1の事業です。エチレンを原料とする独自の製造プロセス「新エチレン法(アルファ法)」は、圧倒的なコスト競争力を誇り、大幅なGHG排出量削減を可能にします。
現在検討中の米国ルイジアナ州における工場の新設投資は、投資額が数千億円に及ぶものの、MMA事業の中長期的な成長のためには重要な投資であり、収益性を検証しながら前向きに検討しています。可能な限り早期に最終判断したいと考えています。(※ 2024年7月現在)
ベーシックマテリアルズ&ポリマーズ
マテリアルズ&ポリマーズ事業:グリーン化に向け再編を加速
石化業界においては、国内市場の需給ギャップ拡大、中国企業の大増産などを受け、収益環境が急速に悪化しています。加えて、CN・CE実現には莫大なリソース投入が必要なことから、個社での対応は限界があると考えています。
2021年に発表した経営方針「Forging the future 未来を拓く」では、当社グループの石化事業は将来的な分離・独立を既定路線としていましたが、事業を切り離したからといって、そこでCN・CEが達成されるわけではありません。サプライチェーンの川下には、多くのお客さまが存在しますので、もし石化事業のCN化・CE化ができなければ、お客さまにも深刻な影響が及ぶことを懸念します。グループ内で川下に位置する高機能材料のグリーン化という観点からも、重要なことは逃げずに責任を持って石化事業のグリーン化を推進することだと考えています。そしてそのためには、他社との連携・再編が不可欠です。縦横に連携しながらCN・CEを推進していきたいと思います。
私たちが構想するアプローチは、他社と開かれた複数のプラットフォームを形成することです。日本政府が2030年度のGHG排出量46%削減(2013年度比)をめざす中、早期にCN・CE対応の生産設備を稼働させるためには、この取り組みを急ぐ必要があります。すでに西日本のナフサクラッカー(エチレン製造設備)について、旭化成㈱および三井化学㈱と原燃料転換などの共同検討で合意し、その具体的方策や将来の最適生産体制について議論を開始しています。茨城県鹿島地区では、ENEOS㈱と共同でケミカルリサイクル設備の建設を進めています。こうした分野は、いずれも日本の化学会社が得意とするところであり、チャレンジであると同時に大きなチャンスと受け止めています。
個社の取り組みとしては、コスト削減や価格交渉を徹底し、抜本的に収益性を高める必要があります。そして、それは十分に達成可能なテーマです。現にこれだけ厳しい環境下でも、2023年度は炭素事業を除き、黒字を確保しました。やるべきことをやれば、石化事業は「儲かるビジネス」になると確信しています。
炭素事業:利益改善に向け構造改革の断行
製鉄原料のコークスなどを扱う炭素事業は、原料炭価格の高騰と海外市況の低迷を受けて、苦戦しています。従来は売却が既定路線でしたが、まずは構造改革を断行し、赤字を出さない企業体質に変えることが急務です。リサイクル(炭素循環)技術によるCEの付加価値創出の可能性についても、積極的に取り組んでいます。
キャッシュ・フロー管理の徹底とROIC経営の導入

より開かれた、力強い組織文化へ
第一に、減点主義の打破です。従業員からの積極的提案を上司や周囲が安易に否定するようなカルチャーは、組織の活力を阻害します。減点主義は言われたことだけをやる、まさに自分なりの思考を奪い、成長への機会を失わせます。
第二に、現場のモチベーション向上です。モチベーションは生産性だけでなく、事故・トラブルの発生にも大きく関わる要素です。人事制度の見直しや女性の活躍支援など、従業員が楽しくいきいきと働ける職場環境を整備するとともに、当社グループには働きがいがあり、成長の実感を味わうことができるということを、広く訴えていきたいと思います。
そして第三に、仕事の自分ごと化です。この自分ごと化に「10年後、事業や会社をこうしたい」という強い想いが加わったとき、仕事は「家業」となります。家業として取り組む意識を持つことで、次の世代にバトンを手渡すように、より良い業績を残したいという責任感が芽生えます。日々の業務において、希望的観測や思い込み、思考停止、想像力の欠如を排し、現実を真剣に見据える姿勢が生まれてくるのです。
こうした風土改革を成し遂げるには、コミュニケーションの活性化が大切です。私自身、毎月、2カ所の国内事業所、1カ所の海外拠点を訪問し、密接な対話などを重ねています。また、本社においても全グループ従業員を対象としたタウンホールミーティングや、少人数でのランチミーティングなど、さまざまな機会を継続して設けていきます。
全てのステークホルダーの皆さまへ
株価は資本市場からのメッセージであり、私はその動向を絶えず注視しています。三菱ケミカルグループの総力を結集し、持続的に利益成長する事業体に当社グループを変えていきます。それが中長期的には、株主・投資家の皆さまのご負託に応えることだと考えます。もう一度、原点に立ち返って再出発した当社グループに、変わらぬご支援のほど賜りますようお願い申し上げます。
PROFILE
筑本学は1988年に三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)に入社して以来、主に石油化学(石化)事業の営業畑を歩む。キャリアの大きな転機となったのは、長年の海外ビジネスの経験で、特に2度にわたるインド駐在。最初の赴任時には、巨費を投じた工場建設プロジェクトに奔走、そして再赴任時には、採算が悪化した同工場を再建に導いた。帰国後は経営戦略部門における責任者として、文中で述べているKAITEKI Vision 30(KV30)の策定や、さまざまな事業の企画・改革に携わる。こうした経験が筑本の血肉となり、経営者としての今日を形づくったと本人は語る。現場で汗をかき、現場の声に耳を傾けることが、筑本の信条であり、それは今後も変わらない。